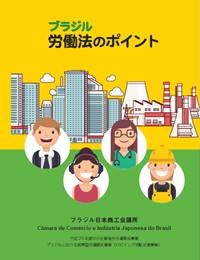>>S&Pがブラジル国債格上げで更にドル安
15日にドル値がR$2.00を割って6年ぶりの水準となるR$1.982となり、昨日は多少ドル高に戻すと大半の金融スペシャリストは予想していたが、S&Pがブラジルの長期外貨建て債務を「BB」から「BBプラス」に格上げしたために、更にドル安が進み、中銀が総額20億ドルのドル介入を実施したにもかかわらず、焼け石に水となり、11ヶ月ぶりとなる1.36%の大幅値下げで、R$1.954を記録した。
ドル安傾向はサラリーマンにとって輸入品の購買力が増加してメリットがあり、政府にとっては輸出企業に対する補償措置を急ぐ必要はないとルーラ大統領は述べて楽観視している。
ドル安に拍車がかかるとスーパーの輸入製品販売増加が明らかであり、パン・デ・アスーカル社では、海外の業者から直接買い付けている米は今年4ヶ月間の売上げが、前年同期比6.7%も伸びているが、商業用冷凍機製造のメタルフリオ・ソルーション社では、ドル安で収益を圧迫されており、コスト削減、輸入部品の使用やイノヴェーション投資で対処せざるを得ない。(17日付けガゼッタ・メルカンチル紙)
>>国会はPACの一環PPI予算増加112億8,000万レアル承認
国会はPACプログラムの一環である投資パイロットプロジェクト(PPI)の予算45億レアルから112億8,000万レアルへの増額を承認、PACプログラム実施に拍車がかかると予想される。
この112億8,000万レアルの増額で、今年のプライマリー収支黒字目標は、GDP比0.45%下げた3.3%に設定されるが、投資増額分はSelic金利引下げで、国債金利支払い減額分が想定されている。
今年初めのプライマリー収支黒字はGDP比4.25%に設定され、再度3.8%に見直されたが、PPIプログラム推進には予算が不足していたために、PACの大衆住宅及び上下水道整備に対する州や市町村の負担を軽減する政治駆引きで、連邦予算基本法(LDO)を修正することに成功した。(17日付けエスタード紙)
>>ヴォトランチンはリオに100万トンの製鉄所建設
ヴォトランチングループはリオ州レゼンデ市に10億レアルを投資して、年産100万トンの製鉄所を建設、またバーラ・マンサ製鉄所の生産能力を70万トンに引き上げ、年産30万トンでコロンビア第2位のパス・デル・リオ製鉄の株式52%を獲得して増産に拍車をかけている。
ヴォトランチンの製鉄所新設は、国内資本で最大の生産野力のあるゲルダウ社、世界最大のアルセロール・ミッタル資本のアルセロール・ブラジル傘下のベルゴ社と国内シェアを争うための投資である。
しかし世界的に鉄鋼業界の再編が進んでいる鉄鋼業界において、ヴォトランチンの戦略は後出に回っており、世界ランクの鉄鋼会社の年産は2,000万トンを上回っている。(17日付けエスタード紙)
>>大手スーパーがEコマースでの販売に注目
大手スーパーのパン・デ・アスーカル社は、1995年にネット販売サイトを立ち上げたが、利益率の大きいEコマース販売に注目しており、現在の売上げは全体の1%の1億6,000万レアルであるが、同スーパーのデリバリーサイトPDA及びExtra.comの売上げを5倍にする計画を進めている。
またウォール・マート社もインタネット販売に注目しており、米国のウォール・マート社のネット販売オペレーションを研究しており、今年の年末にはサイトを立ち上げる予定である。
サンパウロ州内にスーパー網を有するソンダ社は、2004年からソンダ・デリバリーを立ち上げて1万点の商品を販売、昨年は前年比48%の売上げ増加を記録、平均購入額は300レアルとなっている。(17日付けガゼッタ・メルカンチル紙)
【 時事評論 】
何の錨、どちらの投錨なのか
デルフィン・ネット元大臣をはじめ多数の経済学者達がそれぞれ矛盾した2つの理論を支持している。
一つは高金利が国内為替のドル下落の主な要因となり、投機を刺激する結果、高金利の恩恵を求めて資本が流入すると言う理論である。デルフィン・ネット氏によると、もし中銀が他国のレベルにブラジルの金利を調整すれば対米ドルのレアル高に終止符が打たれると確信している。
二つ目の理論は米ドル為替レートの下落が(=レアルの高)中銀が実施している金利低減政策よりもブラジルのインフレ低下に貢献しているのだと言う。
もし、この概念をビリヤードゲームに例えれば、おかしい事に気づくことが出来る。黒のボールはまずプレイヤーが白のボールを突かないと落とすことができないことになっている。もし、高金利が米ドルを下落させ、それがインフレ率を低下させているならば、為替ではなく、高金利がインフレを抑えている事になる。
最も適切な言い方からすれば、高金利は対米ドル、レアル高の主要因ではないということだ。この理由は3つのファクターから明白である。
* 貿易バランスの好実績 – 4年連続4百億米ドルを越す貿易黒字がでている。
* 外国からの直接投資の急上昇(今年2百億米ドルを上回ると予測されている)。
* カントリーリスクの低下(現在152)。
これらは現在の世界市場の目ざましい流動性、経済状況の好転と密接に関連しているからだ。
また、金利は事実、需要をおさえ、インフレを抑える効果と同時に貯蓄を刺激するのは論を待たない。この効果さえ無ければ、中銀はインフレ抑制だけに固執、経済成長の為の金利政策をしていない等というクレームは本来無くなるはずだ。
しかし、為替がインフレを抑える主な役割を果たしている事には間違いはない。これは経済学者らが名付けたパス・スルー(Pass Through)なるものであり、為替が物価の変動(上がるか、または下がるか)に影響しているという事である。ドル安は輸入を促進し、商品は比較的安価で国内市場で販売され、このメカニズムが国内競争を起こし、製造業または販売業者の価格を輸入類似品より高値に設定することを不可能としてしまう。
この証拠にトレーダブルな商品が一番インフレを抑えるために、競争原理により寄与しているのだ。サービス業の大半は市場の競争原理が作用せず、学校の月謝は輸入の取引の対象では無いし、まして美容師、医療サービス業なども同様である。
我々が推測できる事では、中銀は為替がインフレ率を低下させているという事実にあまり重要性を感じていないということである。従って、その無関心さが金利の引き下げを遅らせているのではないかという事だ。
この疑問を分野のオーソリティーらに投げかけると、無関心など有り得ないと言う。ただ、世界のどの中銀も物価動向の予測を為替動向に左右され操作する権利は無いとの一点張りだからである。
とにかく、この課題の分析はこのコラムの枠に収める事は無理であろう。
<07年5月13日付けエスタド紙>