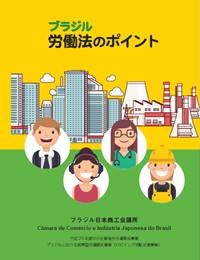>>今年の機械・装置部門が好調
今年初め4ヶ月間の設備投資用などの機械・装置部門は、前年同期比8.6%増加の181億レアルを売上げ、企業家の経済成長の確信に伴って設備投資が回復してきた。
また4ヶ月間の輸出は道路建設用機械、重機、農業機械などを中心に25.5%増加の32億ドルで、主に米国やアルゼンチン向け輸出となっている。
輸入もドル安の為替で米国、ドイツ、日本やイタリアから重機、トランスミッション、工作機械など、前年同期比の34億ドルから26.8%増加の43億ドルと大幅に増加している。(22日付けガゼッタ・メルカンチル紙)
>>ドル安にもかかわらず、貿易収支黒字が好調
今月第3週の貿易収支黒字はR$2.00を割込むドル安にもかかわらず、輸出が33億3,000万ドル、輸入が20億2,900万ドルで13億100万ドルを計上して、今年の週間記録を塗り替えた。
今年の5月第3週までの累積輸出額は、前年同期比19.7%増加の550億1,900万ドル、輸入は26.4%増加の393億2,900万ドルで、貿易収支累計黒字額は156億9,000万ドルに達している。
第一次産品輸出はトウモロコシ、大豆、食肉を中心に前年同期比66.5%、半製品は大豆油、銑鉄、パルプなど52.2%、完成品はガソリン、アルコール、航空機やオレンジジュースを中心に27.8%それぞれ大幅に伸びた。(22日付けエスタード紙)
>>ペトロブラスはアマゾンで天然ガスパイプライン敷設
ペトロブラス社はPACプログラムの一環であるウルク油田からマナウス市までの670キロメートルに24億レアルを投資してネグロ河を跨いで、天然ガスパイプラインを敷設する。
このパイプライン敷設で日産470万立方メートルの天然ガスを輸送、主にマナウス市の火力発電所向けに利用するが、ジーゼル燃料使用と比較して年間12億レアルの経済効果がある。
ペトロブラスは2008年4月を工事完成と予定しているが、雨季に入ると工事に支障をきたすために、天然ガスパイプライン工事遅延の可能性も充分ありうる。(22日付けヴァロール紙)
>>エンブラエルはエグゼクチブジェット機部門でランクを上げる
昨年のエンブラエル社のエグゼクチブ用デラックスジェット機売上げが6億3,700万ドルで、ボーイング社の5億9,200万ドル、エアーバス社の5億ドルを追越して世界ランク6位に上昇した。
昨年のエンブラエル社のエグゼクチブ用ジェット機部門の純利益は全体の15%を占めたが、2016年までには20%の純益を同部門から計上する予定である。
今後10年間のエグゼクチブ用ジェット機の売上げは、1,070億ドルと見込まれており、中国、ロシア、インドやサウジアラビアなどの発展途上国での需要が見込まれている。
エンブラエルは2002年に初めのエグゼクチブジェット機として、レガシージェット機を市場に投入したが、Phenom100型 Phenom300型及び Lineage型ジェット機を2008年から2009年にかけて市場に投入、マーケットシェア拡大を目指す。(22日付けエスタード紙)
【時事評論】
金 利 に 一 刀 両 断
米ドルの下落阻止の対策を要求している大半の企業家と経済学者達は、金利について一刀両断的な緊急引き下げ措置(デルフィン・ネット元大臣によると、メスを入れること)を支持している様だ。
どれだけのカットを要するかは今のところ明らかでないが、金利を他国と同レベルに調整することを提案して憚らない。アメリカの基本金利(現在年間5,25%)から米インフレ率を差し引き(年間2,5%)、ブラジルのカントリーリスク率(1,5%)とブラジルのインフレ率(3%)を加算、単純合計により、海外金利に均等化すれば、SELIC金利はいきなり12,5%から7,5%に削られる事になる。
もしそれが即実行に移されれば、現在採用しているインフレ目標達成システムの継続が不可能な事を認めない訳には行かないに違いない。
理想的な為替率とインフレ率を両立させるにはインフレ目標を年間7%あたりまで上げるか、或いは、緊急措置のため現行の経済政策を支える三本柱の1つ(インフレ率目標達成システム)を諦めなければならないが、屋台骨を揺るがしかねないリスクを伴う危険性がある。
しかし、金利をいきなり7,5%まで引き下げても、その主要因が見つからない限り米ドル回復の達成は所詮無理である。これらの企業家・経済学者達は、米ドル下落の主要因は金利だと思い込んでいる。確かに投資家たちは外国通貨で資金調達を行ない、レアルで国内金融市場に投資を行い、さらに金利の利鞘に食指を動かし外国への(利益、投資、決済などの)資金トランスファーを回避(または延期)する傾向すら見られる。
これら金利の利鞘を求めた投機的なオペレーション案は非常にパワフルであるが、しかし、これはレアル高の要素であっても主要因ではない。莫大な貿易黒字(今年、5百億米ドルに近づくと見られている)と外国からの直接投資の上昇(今年2百億米ドルを上回る予想)などの事実の方がこの問題に繋がっているからだ。
普通、為替を守るために強制的な金利低減を試みた場合、追加工作が必要となる。例えば輸入ショック政策を挙げているデルフィン・ネット元大臣案がそれである。即ち輸入税を強制的にゼロにし、米ドルの需要率を供給率に近づけ、為替レートを正常にする事である。
これは対策の一助にはなっても、しかし、病に一番適した薬を処方するということには勝らない。軌道外の為替が根本的な問題であるとは言い難い。主な原因は製造業の競争力の無さが、安すぎる米ドルによって曝け出されているに過ぎないのである。競争力がないという事は重い税負担、高価で不適切且つ時代遅れのインフラ、サラリーマンの高額な社会負担などに他ならない。つい最近まではこのような問題は、適正とされる好都合な為替レートによって覆い隠されてきたが、それが今不可能になっているのだ。
解決にたどり着くには真因を奥深く追究し、アタックすることであり、今こそ構造改革を果敢に実行する時と言えそうだ。最早政治家達は果たすべき役割から逃げられるまい。
<07年5月19付けオ・エスタード・デ・サンパウロ紙>