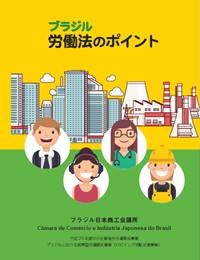ブラジルでもデジタル改革に伴って課税関係が曖昧で問題が発生しており、サービスアプリケーションや3Dプリンターサービス、ロボット、仮想通貨、マーケットプレイスで課税問題が発生している。
リアルタイムでメッセージの交換ができるスマートフォン向けのインスタントメッセンジャーアプリケーションのWhatsAppは、電話に取り替わるツールとなってきており、今年上半期のデーターによる使用料金は77%と電話料金の23%を大幅に上回っている。
2000年の通信関連業界による商品サービス流通税(ICMS)は10.4%を占めていたが、2017年には7.8%まで減少してきており、将来的にどのような課税方法が採用されるのか不透明となっている。
またブラジル国内経済の低迷で失業率が高止まりして源泉徴収個人所得税の大幅上昇は見込めない一方で、一般のドライバーが空き時間と自家用車を使って行うタクシーのようなサービスのUberや2015年にコロンビアで創業された宅配アプリRappi関連で働く人が増加している一方で、個人所得税や社会保障院(INSS)の積立金の増加には繋がっていない。
ソフトウエアやアプリケーションなどのサービス輸入に関する社会統合基金(PIS)並びに社会保障賦課金(Cofins)、サービス税(ISS)、個人所得税(IROF)の課税が曖昧となっている。
10月9日経済協力開発機構(OECD)事務局は、高収益を上げている多国籍大企業(デジタル企業を含む)の消費者向け活動の拠点がどこにあるか、どこで収益を上げているかにかかわらず、確実に納税するために、国際交渉を進める提案を発表した。
この提案は、一部の利益とそれに対する課税権を多国籍企業の市場がある国・地域に割り当てることを提案しており、多国籍企業が物理的に所在していない地域で重要な事業を行っている場合、(1) どこで納税すべきか(「ネクサス」ルール)、(2) 利益のどのくらいの割合に課税されるべきか(「利益配分」ルール)を明確にした新たなルールを創設することで、企業はその国で課税されるべきだと説明している。(2019年10月14日付けエスタード紙)