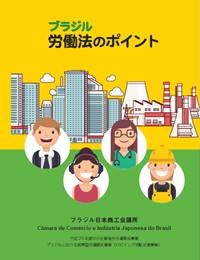国内のあらゆる業界の企業の70%以上が、新型コロナウイルス(COVID-19)のパンデミックが終了した後も全面的あるいは部分的にパンデミック下で導入した在宅勤務という新たな勤務形態を維持する予定。工業部門では、在宅勤務を取り入れ継続する企業の比率はおよそ80%、サービス業では89%に達している。商業は、新しい勤務形態の導入に最も消極的だった。
コンサルティング会社のタレンセス(Talenses)がドン・カブラル財団(FDC)と共同で国内375社を対象に実施した調査で明らかにした。平均すると、すべての業界の従業員の70.3%が在宅勤務中で、工業ではこの比重が3月に3倍に増加した。COVID-19の感染拡大に伴ってブラジル国内で検疫隔離措置が講じられる以前は15.2%だった在宅勤務の導入比率が、現在では50%以上に上昇している。
サービス業界では、同じ期間に在宅勤務の導入比率が25.6%から76.3%に上昇した。さらに第3セクターでは、40%から85%に上昇している。商業の場合、国内の大部分で必須サービスと認められた業態に限り営業が認められている状況のため、在宅勤務で勤務する労働者の比率は22.9%と最も低かった。タレンセ・グループのルイス・ヴァレンテ(Luiz Valente)CEOは、「企業は強制的に変革プロセスに立たされているが、今回の調査では、現在の一連の経験と状況への適応がその後に企業の採用する新たなルーチンに変化するであろうことを示している」とコメントした。
調査対象となった375社の内30社が商業、77社が工業、197社がサービス業、6社が第3セクター、65社がその他。全体の平均で、28%が在宅勤務の導入で問題に直面していると回答した。とりわけ第3セクターでは、全社員向けのインフラの不足(ノートパソコンや電話等)という問題が指摘された。
サービス業界では、他の業界以上にリモートワークが実施できないプロセスで課題に直面した。在宅勤務のモデルに関するポリシーを確立していなかったことは工業も同様だったが、とりわけ商業で大きな課題だと指摘され、経営陣の意思決定に遅れを生じさせた。だが、すべての観点から見た課題の平均を大きく上回り最大の問題だと指摘されたのは、リモートワークによるガバナンスに関連した、企業文化と言える問題への対処である。「この状況により統一的な形態で全員を組織に統合することが求められたが、今、それを実現する能力、実現しているか良好に実現するかは、組織文化に左右される。既に組織化されていれば、より迅速に対処できた」と、FDCのポール・フェレイラ(Paul Ferreira)リーダーシップセンター理事は話す。
新しい組織では、例えば、選択プロセスへの適応やオンライン・フォーマットへの移行、リモートワークを通じた新しい従業員の採用(オンボーディング)などが求められた。「企業は、それまで日常業務にしていなかったり馴染みがなかったり、経験のなかったオンライン手続きへの移行というプロセスの扉を開いた」とヴァレンテCEOは言う。35%以上の企業が、リモートワークで100%のプロセスを処理していると回答した外、34.7%の企業が新規の雇用を中断していると回答した。商業とサービス業では、欠員補充の凍結が過半数の組織に影響した。
オンボーディングでは、57.6%の企業が通常業務の中に新たな従業員を割り込ませ、この従業員に組織の一員だと実感させるのに苦労したと回答した。必須の研修の実施は、あらゆる業界で大きな課題だと指摘された。平均すると、26.4%が研修を中止、42.9%がオンラインで全面的あるいは部分的に継続している。一連の変革や適応がCOVID-19後の企業の世界のルーチンに影響すると企業は確信していることに関連し、ポール・フェレイラ理事は、どのように取り込まれ、ポリシーとして成立するかにつながるのかは、企業経営者が得た教訓にあるとコメントした。「これらの慣行の多く、とりわけ成果をもたらしているものは、今後も維持されるだろう。むしろ根底にある問題は、人事と経営陣が、例えば危機的状況にない状況下でリモートワークを通じた作業の生産性や人材の採用、労働意欲といった問題をしっかりと分析する必要があるということだ」と評価した。(2020年4月23日付けバロール紙)