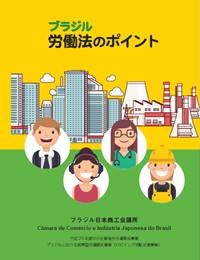金融部会(種村 正樹部会長)は、2020年2月4日午前11時から11人が参加して開催、初めに2020年度の金融部会執行部として、東 邦彦部会長(Tokio Marine Seguradora S.A.)、北村裕行副部会長(ブラジルみずほ銀行)、小見山真弥副部会長((Tokio Marine Seguradora S.A.)を選出。今年上半期の業種別部会長シンポジウムにおけるマクロ経済概要、銀行業界動向、保険業界動向の発表に対するアンケート調査の発送、結果の取り纏めなどについて説明。また昨年の金融部会の活動報告では10月25日のフィンテックセミナー「Future of Finance」講演会開催、10月18日の懇親昼食会での三菱UFJ銀行グローバルマーケットリサーチエコノミストのCliff Tan氏は、テーマ:「米中貿易戦争の中南米市場(特にブラジル)への影響」講演会開催を報告した。
参加者は東新部会長(ブラジル東京海上日動火災保険)、北村裕行新副部会長(ブラジルみずほ銀行)、小見山真弥新副部会長(ブラジル東京海上日動火災保険)、種村前部会長(Banco Bradesco)、津田氏(Banco Bradesco)、安田氏(Sompo Seguro S.A.)、長野氏(三井住友保険)、栗原氏(三井住友銀行)、白石調査員(サンパウロ総領事館)、平田事務局長、大角編集担当。

東 邦彦部会長(Tokio Marine Seguradora S.A.)、


Fotos: Rubens Ito / CCIJB