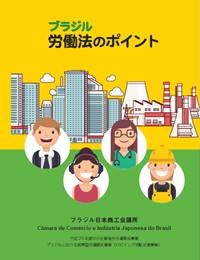コンサルタント部会(渡邉裕司部会長)主催の「J−SOX(内部統制の評価と監査)及び日系進出企業への影響」と題して、9月19日午後4時から会員51人が参加、初めに渡邉部会長はエンロン、ワールドコムの粉飾決算などで生じた投資家の不安をなくするために、内部統制を強化する責任が企業にあり、来年4月以降の事業年度からの施行される金融取引法で内部統制制度の適用を受けるのを前に、今回のセミナー開催を行なうと経緯を説明した。
講演は日本語がデロイトの日系企業サービス部の都築慎一取締役、ポルトガル語がが同社企業リスクサービス分野パートナーのロナルド・フラゴーゾ氏が担当、初めに内部統制の目的として、業務の有効性及び効率性、財務報告の信頼性、事業活動に関わる法令の遵守、資産の保全について説明した。
内部統制の基本的要素として統制環境、リスクの評価と対応、統制活動、情報と伝達、モニタリング、ITへの対応を挙げ、米国では内部統制強化を実施した企業は、上場企業の企業価値の平均を10%以上伸ばして、効果を上げていると説明した。
海外の子会社がJ−SOX法の適応を受けるのは、本社の連結売上げ高の3分の2までの範囲の重要な事業拠点であり、従来の財務諸表のほかに内部統制報告書の作成、それに対する監査報告書を新たに作らなければならないが、ドキュメントの作成、トレーニングなど煩わしい作業が山済みされており、外部委託でのサポートがないと不可能に近い述べた。
質疑応答ではシカゴのデロイト日系企業サービスグループの久保康パートナーは、重要ポイントとして3分の2までの売上範囲に入る子会社であるかどうか、ドキュメンテーションの作成は経験が必要、経営者評価は監査機関に依頼することと締めてセミナーは6時過ぎに終了した。

中央が講演者のロナルド氏/右が都築氏

日本語とポルトガル語で行なわれたセミナー

左からデロイトの中村取締役/シカゴの久保康氏/平田事務局長

熱心に講演を聞く参加者