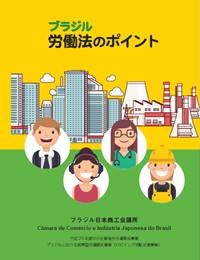連邦政府の国債発行による対内公的債務残高は、昨年末よりも9.63%増加に相当する1,050億レアル増加して1兆1,980億レアル、債務増加のうち686億5,000万レアルは債務残高の金利であった。
連邦政府の年間金融プログラム(PAF)では、年末の負債は1兆3,000億レアルまで許容範囲となっているが、6月の対外債務残高1,264億4,000万レアルを合せた負債総額は、すでに1兆3,200億レアルに達している。
6月のSelic金利連動国債の比率は、前年同月の42.52%から34.06%と大幅に減少したが、確定金利連動国債は31.45%から38.71%、消費者物価指数連動国債は21.73%から23.88%とそれぞれ増加、昨年末の発行国債の平均償還期間は、36.4ヶ月から6月は51.94ヶ月と大幅に償還期間が伸びている。(27日付けエスタード紙)