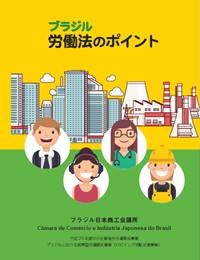商工会議所の懇親昼食会が7月13日正午からシーザービジネスホテルに104人が参加して、バイオエネルギー生産者連合(UDOP)のジョゼ・カルロス・トレード会長の「サンパウロ州西部に於けるバイオエネルギー部門の成長の見通し」と題する、ブラジルが世界の牽引車となるバイオエネルギーの興味ある話に熱心に聞入っていた。
トレード会長の講演の冒頭でUDOP加盟のエタノール・砂糖精製工場は62ヵ所で、そのうち1ヵ所は動物の脂肪から採集したバイオエネルギー工場を擁していると連合の規模を説明、今後のバイオ燃料生産の見通しとして、2003年のバレル当りの石油価格は25ドルであったが、今では70ドル以上まで高騰して再生可能なバイオ燃料の必要性が高まっており、カトリーナ台風などの多発、アマゾン流域の旱魃や海水面上昇などの温暖化が進んでおり、それを阻止するためにも再生可能なバイオ燃料の増産加速化は避けられないと強調した。
また世界的に石油からバイオ燃料使用を実施している国にはブラジル、米国、スエーデン、タイ、オーストラリア、カナダ、検討しているのはアルゼンチン、キューバ、日本、ドイツ、ニュージーランド、ロシアなど多くの国がバイオ燃料使用を研究して再生可能燃料生産に注目している。
コモデティー商品になりつつあるエタノールの生産は、2000年の105億リットルから今年は177億リットル、2012年には380億リットルでそのうち100億リットルが輸出向けとなり、50億リットルから60億リットルが日本向け輸出、今年の砂糖の生産は2,980万トン、2012年には3,850万トンの生産が見込まれている。
ブラジル全国のエタノール精製工場は340ヵ所で、そのうち5州から構成される中南部地域には228ヵ所あるが、生産量では全国の89%を占めており、サンパウロ州単独では生産量の74.76%を占めており、今後5年以内に建設される精製工場107ヵ所は全て中南部地域に集中、ゴイアス州、南マット・グロッソやミナス州での建設が進み、サンパウロ州の寡占率は52.88%まで低下すると予想されている。
一般的に砂糖キビ栽培のモノカルチャーになってしまうのではないかと危惧されているが、昨年の砂糖キビ栽培の耕作面積はブラジル国土の僅かに0.73%であり、2012年は放牧地の転用で1.21%を占めるに過ぎない。
現在のブラジル全国の砂糖キビ栽培はUDOP本部のあるアラサツーバ市を中心とした半径400キロメートル内で、ブラジルの生産の88%が集中、今後は更に伝統的に牧畜業が盛んなサンパウロ州西部の放牧地が砂糖キビ栽培への転用で、大幅な増産が予想されている。
2012年のブラジルの砂糖キビ栽培耕作面積は、現在の600万ヘクタールから1,033万ヘクタールに増加してバイオジーゼルを7億2,800万トン生産、バイオ燃料による電力エネルギーは2万4,000メガワットで、電力輸出はイタイプー発電所の2倍に相当する1万8,000メガワットと計り知れない潜在的ポテンシャルがあり、総額420億レアルの投資及び年間90億レアルの税収となる。
UDOPではサンパウロ西部地域のすでにある小規模の砂糖精製工場へのサポートで、エタノール工業の創出を積極的に進めるが、チエテ河−パラナ河水路での運搬ロジスティック、港湾とのエタノールパイプラインが敷設されているパウリーニャとアラサツーバ間及びパウリーニャ−セナドール・カニェード間のパイプラインの建設や鉄道網の改善が必要である。
また民間企業並びに大学とタイアップしたバイオジーゼル研究センターの設立による技術者のレベルアップ、インフラ面ではエタノール栽培従事の社宅、健康プランの充実、基礎教育の強化、保健衛生など色々な課題があるが、敷地面積が100万平方メートルの砂糖キビ技術センターを建設して敷地内にバイオ研究センター、400人収容の研修生のためのホテル、大学、ブラジル農牧調査研究公社(Embrapa)用敷地、農産品展示場などUDOPでは地元のアラサツーバに建設、更なるバイオ燃料技術、雇用創生、技術者のレベルアップを計る壮大な構想を持っており、ブラジルがバイオ燃料で世界のリーダーになり続けることができる確信が持てる講演であった。
懇親昼食会の司会は平田藤義事務局長が務め、初めに講演者であるバイオエネルギー生産者連合のジョゼ・カルロス・トレード会長、帰国するブラジル日本大使館の大竹茂公使、トレード会長紹介の金沢登紀子サンパウロ総領事館調査員を紹介した。
連絡事項では土肥克己領事が文協で投票が行われる7月13日から21日までの第21回参議院議員通常選挙及び7月18日から21日までの衆議院議員補欠選挙の案内、宮田次郎企画戦略委員長が8月3日の業種別部会長シンポジウムの案内、渡邉裕司ジェトロ所長が10月に機械・金属部会共催のミナス産業視察ツアー、8月末に開催されるジェトロのエタノール視察ミッションへの参加、またチリ、ボリヴィア並びにペルーの地政学的軋轢について説明した。
会社代表交代挨では味の素の酒井芳彦社長が帰国挨拶、新谷道治新社長が就任挨拶、三菱重工の大隈広視社長が就任挨拶を行い、新入会員紹会ではモラーレス・ピトンボ法律事務所のジョー・タツミ氏が入会挨拶を行い、田中信会頭から会員証が授与、最後に田中会頭が大竹公使に対して歓送の辞を述べ、大竹公使は帰国挨拶を行なった。

左から平田事務局長/大竹公使/金沢調査員/講演者のトレード会長/田中会頭









 サンパウロ新聞社社長高坂・ジベルです。ブラジルの日本語新聞として終戦直後の1946年創立され、今日まで62年間日系コロニアの耳となり、目となり活動してまいりました。外国出身の私たちの誇りである皆様が持っている日本の文化の意味と重要性を今回、もっと深く考えて欲しいと思っています。
サンパウロ新聞社社長高坂・ジベルです。ブラジルの日本語新聞として終戦直後の1946年創立され、今日まで62年間日系コロニアの耳となり、目となり活動してまいりました。外国出身の私たちの誇りである皆様が持っている日本の文化の意味と重要性を今回、もっと深く考えて欲しいと思っています。 レアンドロ・ハットリ会頭はブラジル日本青年会議所は 25年前に、ブラジル日本商工会議所の後押しで設立、25周年の6月には商工会議所の協力で色々なエヴェントを検討しており、3月にはレナート・西村氏を招いてキャリアに関する講演会、4月にはヤスシ・アリタ氏を招いて人生設計に関する講演、5月にはサトシ・ヨコタEmbraer副社長を招いて講演会を実施して活発に会議所活動を推進していると説明した。。
レアンドロ・ハットリ会頭はブラジル日本青年会議所は 25年前に、ブラジル日本商工会議所の後押しで設立、25周年の6月には商工会議所の協力で色々なエヴェントを検討しており、3月にはレナート・西村氏を招いてキャリアに関する講演会、4月にはヤスシ・アリタ氏を招いて人生設計に関する講演、5月にはサトシ・ヨコタEmbraer副社長を招いて講演会を実施して活発に会議所活動を推進していると説明した。。