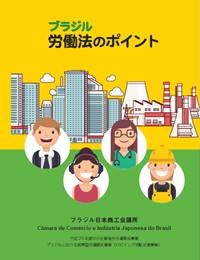ロベルト・ロドリゲス*
豚コレラが、中国における豚肉の生産と消費に対して甚大な被害を及ぼしており、これに伴って発生する中長期的な影響は完全に評価を終えていない状況だ。この恐ろしい病気(と言っても人類に対する直接的な感染の脅威はなく、豚にとっては死に至るものである)が抑え込まれ撲滅できるかにかかっている。この疫病は、既に欧州でも発生が確認されており、アジア地域にとどまらない、世界のすべての地域にとって潜在的な脅威なのだ。
仮に直ちに抑え込みに成功したとしても、既に何1,000頭もの親豚が殺処分され新規生産基盤が縮小しており、生産のサイクルが破綻したことで生産状況が正常化するのにはおよそ3年はかかる。
しかし、もし本当に今の時点で飼育頭数が大幅に減少したのであれば、同様に中国の生産者による大豆とトウモロコシの需要も減少するはずで、輸出の減少とこれらの製品の値下がりにつながる。すでにコーヒーと牛乳、サトウキビで記録されてきたような、我が国の農業輸出の落ち込みという状況が拡大するはずだ。ブラジルの農業輸出では大豆が全体を牽引していること、そしてはるか遠くの中国が最大の輸出先国であるという点に注意を払うだけの価値はあるだろう。
ブラジルは、わずか数か月で食肉生産を拡大できるし、この場合、輸出している穀物の大部分を通常の条件で国内市場に振り向けることになる。そして食肉輸出は、付加価値という点で追加のアドバンテージとなる。大豆とトウモロコシは、ここで生産された食肉に組み込まれることになる。
これを実現するには、企業の財務状況がひっ迫している状況で生産拡大に向けた生産者の投資という与信供与に対する需要につながる問題は言うに及ばず、ブロイラーと豚の確保にとどまらない、より多くの食肉加工会社に対する輸出認可に向け最大限に迅速な政府の交渉が求められる諸条件のクリアが必要になる。
この道筋をつけるため、状況のより良い理解と必要とされる合意をまとめようと、テレーザ・クリスチーナ農務大臣が中国とアジア諸国を訪問している。
だが我々は、例えばアメリカと欧州連合(EU)も同様に、この機会をうかがい、同じ方向に駆け出していることを忘れてはならない。そして5月10日に中国から輸入する2,000億ドルの製品に対して関税を10%から25%に引き上げるとドナルド・トランプ大統領が発表したアメリカの場合、食肉のより大きな供給という提案が「貿易戦争」の休戦を決定づける可能性がある、ということだ。
そのため、収益という点からブラジルの農家には脅威であり、深刻な被害を回避するため、迅速に対応する必要がある。
そして、アグリビジネスの国際市場が持ついくつかの局面について、分析するだけの価値がある。この活力に満ちた業界の輸出で投機的な手法が発展してきたことは知られている。その作用もあって、2000年に200億ドルを輸出していたブラジルのアグリビジネスは、2018年には、20年足らずで5倍となる1,000億ドルを記録した。ただ、これがブラジルにあふれんばかりの誇りを与えてはくれるにしても、競合する国々も同様に成長したのだ。
主な食肉(牛肉及び鶏肉)の場合、シェアも失っている。農務省の最新データによると、鶏肉では、2010年に世界の鶏肉貿易の41%をブラジルが占めたが、2018年には31.2%に低下した。そして牛肉の場合、同じ期間に23.7%から16%に下落した。
言い換えると、ブラジルは著しい進展を記録したものの、強豪国も寝ていたわけではなく、むしろブラジル以上に成長したということだ。ブラジルは世界の食肉貿易で依然としてトップを走っているが、次第に、言葉の遊びではなく文字通り「痩せつつある」のだ。
迅速かつ適切に対応すればプラスに利用できる豚コレラは好機となるという意味で、連邦警察が立ち上げたカルネ・フラッカ汚職捜査とトラパッサ汚職捜査のような不幸な災難は「体制」を強化する。
それは、政府と民間部門がうまく調和し奏でる交響楽であり、別の生産チェーンにおいても同様の対応が可能だと実証できるだろう。農産物の世界貿易においてブラジルは極めて重要な存在だと認識するのは重要なことだが、そうした製品は半ダースしかないのだ。すなわち、大豆複合品、食肉、コーヒー、砂糖、オレンジジュース、トウモロコシだ。むしろ、同様の地位を確保するのに、フルーツと綿花、魚介類、カカオ、パーム油、紙パルプ、ゴム、花卉、その他の穀物、牛乳といった品目には、取り組むべき余地がまだ多く残されている。
そして、隊列は進む。我が国は食糧安全保障において、最大のパートナー候補となるべき国だが、疾走する原石のダークホースを数多く保有している。(2019年5月12日付けエスタード紙)
*元農務大臣でゼツリオ・バルガス財団のアグリビジネスセンター・コーディネーター。