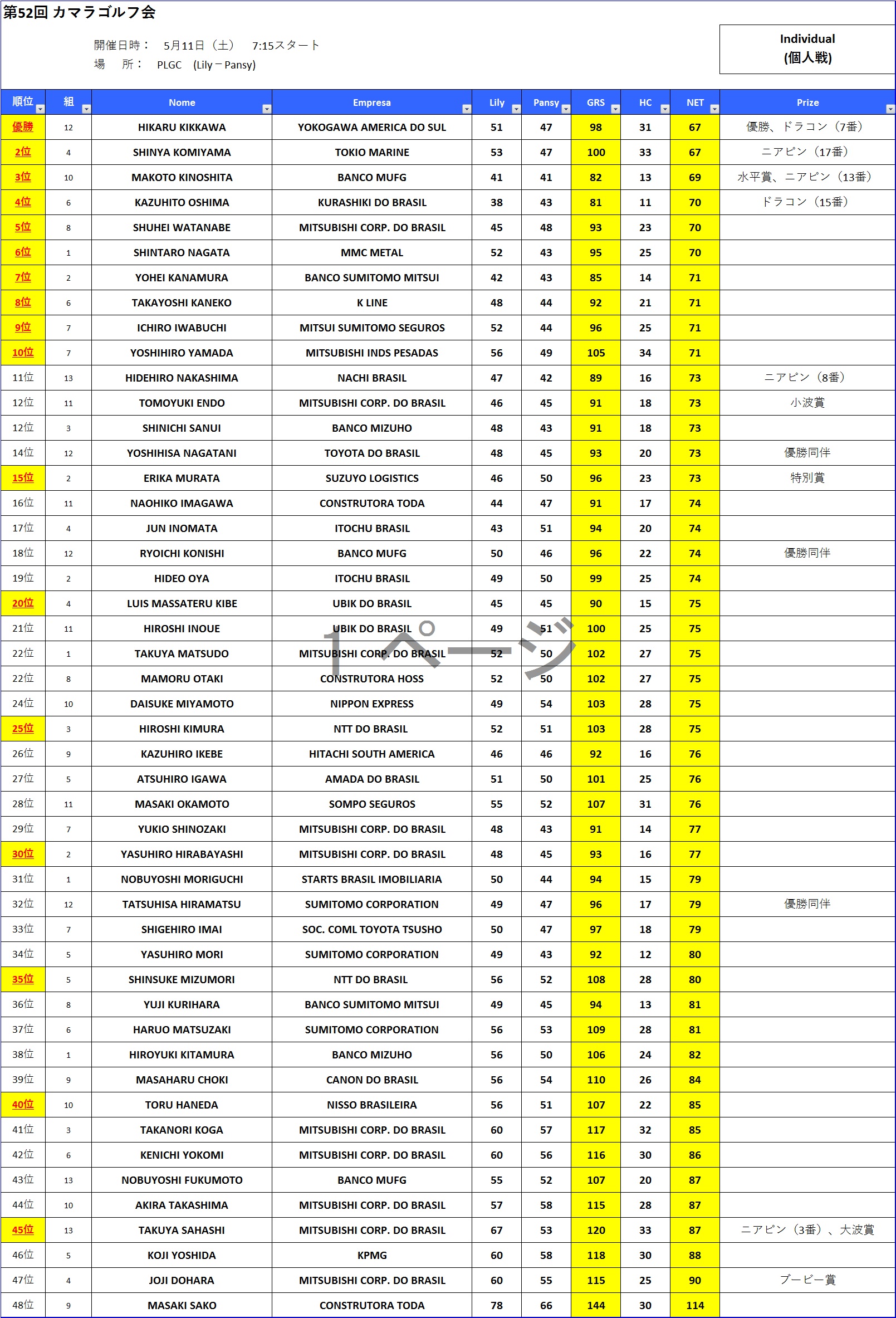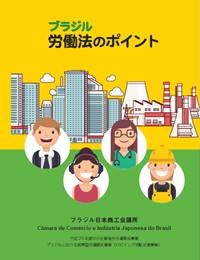元役員と元事業家をマネージャーに据え、様々なグループが共同で投資し、投資先を多様化させている。
ブラジルのスタートアップに対してベンチャーキャピタル・ファンドが投資する資金のほぼすべてが、技術系企業の創業者とその他の機関投資ファンドらから国際市場で調達された資金である。この業界の先駆者のひとつモナシーズは、7ファンドを国外からの資金だけで設立、その1つに限り国内資本との合資としている。
その最後の国内外から資金を調達したファンドでは、インスタグラムの創業者でシリコンバレーで最も影響力を持つブラジル人の1人、マイク・クリーガー氏のようなブラジルの富豪と事業家などから1億5,000万ドル(5億9,400万レアル)を調達した。ブラジルでスタートアップが爆発的ブームになる以前の2005年に設立されたモナシーズは、ブラジル生まれのユニコーン企業、99に投資した。同様に、ユニコーン企業の仲間入りを果たしたコロンビア資本のラッピにも出資している。
マッキンゼーとアメリカのファンドであるジェネラル・アトランティックといった企業で経歴を持つエリック・アーチャー氏とウルトラ・グループの経営権を持つファミリーの資産を相続したファビオ・イゲル氏が設立したファンド・マネージャーの最初の投資は、経営パートナー自身が設立した教育会社で、これは当時、投資先となるスタートアップのオプションがなかったことによる。だがこれ以降、ファンド・マネージャーはラテンアメリカで88社に対して既に資金を提供している。現在、同ファンドの投資ポートフォリオには60社が名を連ね、この内42社がブラジル国内企業である。これらの中には、グロー(ブラジル企業のイエローとメキシコ企業のグリンの合併により誕生)やロジ(配達スタートアップ)、ネオン(デジタル銀行)、ヴィヴァ・レアル(不動産)のように、新しいユニコーン企業の座を射止める有力候補が控えている。
ブラジル国内に潤沢な資産を持つ別のファンドが、アルゼンチン系カザック・ベンチャーズである。同ファンドは、メルカード・リブレの元役員と創業者によって立ち上げられた。2011年に設立されたこのファンド・マネージャーは、既にアメリカと中国で3つのファンドで資金を調達しており、その総額は4億3,000万ドルに達する。カザックの経営パートナー、サンチャゴ・フォッサッティ氏によると、これらの資金を60社に投資しており、この内3分の2がブラジル国内だという。これらの中には2社のユニコーン企業が存在する。すなわち、ヌバンクと、スポーツジムのマーケットプレイスでこのほど10億ドル企業の仲間入りをしたジムパスである。
起業の世界でよくあるように、これらのスタートアップには別の、重要な大規模な投資グループも参画している。すなわちバロール・キャピタル・グループとレッドポイント・イーベンチャーズである。バロール・キャピタル・グループは、クリフォード・ソーベル元駐ブラジル・アメリカ大使が設立したもので、既にブラジル国内の30のスタートアップに投資している。ジムパス以外に同ファンドは、ブラジルのポータブル決済端末のユニコーン企業、ストーンにも出資している。
バロール・キャピタル・グループの経営パートナーであるマイケル・ニクラス氏は、当初はブラジルのプライベートエクイティへの投資というアイデアで始まったと話す。「ところが、ベンチャーキャピタルにもビジネスチャンスがあることが分かり、2012年に市場の様子を見るためにファンドを構築した」という。他のファンドと異なり、資金の調達はブラジル人を対象にした。
レッドポイント・イーベンチャーズも同様に、2012年、シリコンバレーの2つのファンド・マネージャー、レッドポイント・ベンチャーズとイーベンチャーズが提携して設立された。「これらのファンドの設立者は、2010年、『飛び立つキリスト像』が世界を駆け巡った時にブラジルへ進出した。だが、ブラジルの複雑な事情から現地の人間がプロジェクトの面倒を見る必要性を理解した」と、レッドポイント・イーベンチャーズでロメロ・ロドリゲス氏とパートナーを組むアンダーソン・ディース氏は言う。同ファンド・マネージャーは、既に31社に投資している。「当初から目的は、シリコンバレーの優れた慣行と経験をブラジルに持ち込むことだった」。
「様々なファンドがブラジルに進出を始めたのは2010年、『飛び立つキリスト像』が世界を駆け巡った時だが、ブラジルの複雑な事情から現地の人間がプロジェクトの面倒を見る必要性を理解した」 レッドポイント・イーベンチャーズの経営パートナー、アンダーソン・ディース氏(2019年5月12日付けエスタード紙)