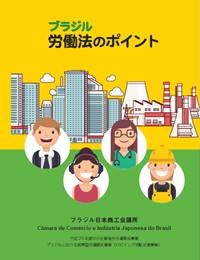平成30年度官民合同会議が2018年12月13日(木)13時から15時45分までジャパン・ハウスで開催され、山田大使、高橋 外務省中南米局審議官をはじめとする官側からの出席者と、民側からブラジル各地の商工会議所代表が参加し、それぞれ発表と意見交換が行われた。
山田 彰大使による冒頭挨拶で、日伯移民110周年を迎えた今年、第8回世界水フォーラムにおける皇太子殿下のご来伯、眞子内親王のご来伯、オリヴェイラ上院議長の訪日,5月のヌネス外務大臣の訪日と河野外務大臣の訪伯、ボルソナーロ次期大統領の訪日、など多数の要人往来に関し、一連の行事への日系企業の協力に改めて謝意を表した。また2018年のブラジル経済は予想程の回復には至らなかったものの、ボルソナーロ次期大統領政権への期待感、特に日本への評価が高いことや、産業強化のための施策を行うビジネスフレンドリーな姿勢など、年金改革、税制改革の実現を含め明るい兆しがある、とした。日伯賢人会議、日伯経済合同委員会、日伯貿易投資・産業協力合同委員会、インフラ作業部会、日伯農業対話など、引き続き日伯間の対話の枠組みの中で、日系企業と連携しながら2国間関係強化に努めていきたいとし、挨拶を締めくくった。
続いて高橋 克彦 外務省中南米局審議官による外務本省からの報告では、ボルソナーロ次期大統領新政権との関係構築強化に向け、就任式への特使派遣を検討していること、また来年2019年に日本がホスト国となり開催される大阪G20でのハイレベル交流をどのように進めていくかを検討中であることが述べられた。また日本メルコスールEPAに関して、日本やメルコスール各国の産業界から強い期待があること、また重要なアジェンダであることは日本側でも承知しており、関係省庁と経済界で協議を行いながら見極めている時期、とした。また最後にアルゼンチンG20で発表された日・中南米「連結性強化」構想について説明し、2014年の安倍総理来伯時に提唱した「3Juntos」の次なるステップとしての構想であり、「自由で開かれた経済システム」、「ルールベースの多国間主義」、「SDGsの実現」の3本柱を掲げ、各国で積み上げた「3 Juntos」の成果を地域全体として改めて総括し次なる協力の段階へと深化させるものである、とした。具体的な施策については今後検討が進められていく。
在ブラジル日本国大使館からの報告では、池田 英貴参事官と大田 啓書記官より説明があり、第2回日伯インフラ協力会合の評価、自衛隊記念品レセプション、天皇誕生日レセプションなどにおけるジャパン・ブランドのPR、日本の農林水産品・食品の輸出促進、大使館による日本企業の支援体制について説明を行った。
続くJICAの活動説明では、都市問題と環境・防災対策、投資環境改善、三角協力支援を重点をおく援助分野としており、特に投資環境改善に力を入れていることを説明。会議所インフラワーキンググループでAGIR提言活動も行っており、ブラジルのどのようなルールが投資の阻害となっているかなど企業からの積極的な情報提供を求めた。日本との経済関係強化に資するインフラへの投資、日本の技術やノウハウが活用できる事業に供与する円借款、海外投融資の説明の他、民間連携事業の一環として「中南米日系社会との連携調査団」の派遣を過去5回行っておりその成果として連携事業が複数件実現していることを説明。企業や団体との協働型事業では企業や団体との連携事業を紹介し、引き続き企業活動に寄り添った活動をしたいきたい、として締めくくった。
JBIC片山 周一駐在員によるブラジルにおけるJBICの活動説明では、JBICのミッションとして「日本にとっての重要な資源の海外における開発および取得の促進」、「日本の産業の国際競争力の維持および向上」、「地球温暖化の防止等の地球環境の保全を目的とする海外における事業の促進」、「国際金融秩序の混乱の防止またはその被害への対処」の4つがあり、具体的な金融メニューを紹介。またブラジル連邦政府との年次政策対話の枠組みや日伯賢人会議への参加、BNDESとの連携、インフラ事業の事例、ブラジルの主要資源会社との連携など活動実績を報告した。
JETROからの報告では、大久保 敦JETROサンパウロ事務所長が今後の取り組み基本方針として「日本企業への変貌するブラジル情報の提供」、「変化が期待されるビジネス環境整備への対応」、「日系社会をハブとした日本企業のビジネス支援体制の強化」、「貿易投資分野における新政権との関係づくり」を挙げ、具体的な取り組み活動案として「対日投資」、「農水輸出」、「海外展開」、「イノベーションの創出支援」、「通商政策・調査」事業へ注力していくことを説明した。
ここまでの発表に関する意見交換の部では、ボルソナーロ新政権の閣僚人選と日本企業への影響、中国企業勢進出の影響、アメリカとの関係性、ブラジルの芋焼酎輸入規制改善などについて意見交換が行われた。
後半の商工会議所からの報告の部では、まずはじめにアマゾナス日系商工会議所 後藤 善之会頭より報告があり、眞子内親王もご参加された日伯移民110周年企業式典の開催、会員企業の推移と内訳、サッカーワールドカップ需要やトラックスト、税関ストの影響、工業団地内での安全対策、マナウス総領事館と連携したインフラ整備、また日系企業の安全性確保やより良い企業活動のため会員企業同士のチームワークの重要性を重視した活動を行っていることが説明された。
続いて和田 好司 南伯日本商工会議所会頭が報告を行い、南伯会議所の設立の経緯、会員企業数推移、日本との姉妹都市提携への取り組みについて説明を行った。
パラナ日伯商工会議所の大城 義明会頭は、JICAやJETRO、大学研究機関との連携、スマートインテリジェンス、都市開発事業、健康・環境事業、小商業の発展等を目指し活動を行っていることを報告した。
続く旭 俊哉 リオデジャネイロ日本商工会議所会頭は、会員企業推移と活動実績、安全対策委員会の取り組み、ビジネス環境整備への取り組みなどについて説明を行った。
パラー日系商工会議所の山中 正二副会頭は、ブラジル政権の交代を好機ととらえ治安対策、森林破壊への対策と環境事業などについて報告、提案を行った。
最後にブラジル日本商工会議所から「日メルコスールEPA活動について」発表を行い、冒頭の松永 愛一郎会頭挨拶で日メルコスールEPAにまつわるこれまでの日伯間の取り組み経緯を説明し、日メルコスールEPA準備タスクフォースの発足と構成、メルコスール全土の日系企業を対象に行った意識調査結果を踏まえた形で「日本メルコスールEPAの早期交渉開始を求める」提言書が菅 官房長官へ手交されたことを報告。続いて二宮 康史 企画戦略副委員長からタスクフォースの活動説明があり、今年2月から10月までアルゼンチン、サンパウロで実施されたEPAに関する知識の啓蒙と情報提供目的とした勉強会、また今年5月にブラジル、アルゼンチン、パラグアイ、ウルグアイのメルコスール4か国に進出する日系企業を対象に実施したEPAに関する意識調査で、74%の回答率のうち実に84%が日メルコスールEPAの必要性を感じているとの結果がでており、その結果を第21回日伯経済合同委員会および第25回日亜経済合同委員会において共有し、それぞれ共同声明として日メルコスールEPA交渉開始を推進することが合意された旨説明している。その結果を踏まえ経団連と日商の連名による「「日本メルコスールEPAの早期交渉開始を求める」提言書が菅 官房長官へ手交されており、現地企業の声を日本に届けるタスクフォースの活動を日本側と連携する形で引き続き活動を続けていくことが報告された。 平成30年度官民合同会議 会議所発表資料
平成30年度官民合同会議 会議所発表資料
後半の部の意見交換では、来年はアマゾン入植90周年にあたり日伯交流強化のためのまた一つよい機会になるであろう、と山田大使より発言があり、また環境保護・農業開発の分野ではボルソナーロ新政権において産業の発展と環境保護が両立されるような施策が行われていくことを期待する旨、日伯2国間EPAを示唆するような発言もボルソナーロ次期大統領からあったがいずれにしても今の時点では何ら明確に決定されていない旨述べられた。高橋審議官からは先日提言書の手交を日本側でも真剣に受け止めており適切な時期に活動が始められるよう動きを進めて行きたい、また外務省内で官房審議官危機管理担当も兼任していることから安全対策についても引き続き尽力していきたい旨が述べられた。また併せて安倍首相による日・中南米「連結性強化」構想については必ずしもEPAに限らず租税条約や投資協定、TPPへの新規参入などあらゆる可能性をオープンにした構想であることも説明された。2018年の民間による日メルコスールEPA推進の動きは大変意義があるものであり、日本政府としてもビジネス環境整備について粘り強くブラジル政府側へ働きかけを行っていく旨山田大使から述べられたのをうけて、ブラジル日本商工会議所 平田事務局長より、仮に日メルコスールEPAを締結したとしても日系企業の進出増加へと直結するものではなく、むしろ年金改革、税制改革などのブラジル国内の諸改革も同時に進め投資環境、ビジネス環境を整えていくことの重要性が指摘された。また平田事務局長は、当所メディカル分科会が進めるリオのInmetro(ブラジル国家度量衡・規格・工業品質院)、ブラジリアのAnvisa(ブラジル国家衛生監督庁)との積極的な政策対話を紹介し、特にInmetroにおける星野リオデジャネイロ総領事の協力へ謝意を表し、またブラジルの産業・サービス分野の発展に大きく貢献した者へ授与されるバロン・デ・マウア勲章を当所松永会頭が前日に綬章したことを報告、山田大使にもご参加頂いたセアラ州ZPE(輸出加工特区)への視察などの会議所活動が高く評価された結果であると説明を行った。
最後の野口サンパウロ総領事によるまとめの挨拶では、日伯110周年記念事業における日系企業の協力への謝意、ブラジルの治安状況についての説明、日系社会との連携による人材育成等の活動、日メルコスールEPA推進に関する県連からの要望書などを含む各県の動き、ジャパン・ハウスの入場者推移や企業活動のプロモーション、サンパウロ州マリリア市と大阪府泉佐野市の姉妹都市協定について報告を行い閉会とした。
 平成30年度官民合同会議 議題
平成30年度官民合同会議 議題
 平成30年度官民合同会議 参加者リスト
平成30年度官民合同会議 参加者リスト

 ( fotos: Seidi Kusakano)
( fotos: Seidi Kusakano)




























 ( fotos: Seidi Kusakano)
( fotos: Seidi Kusakano)