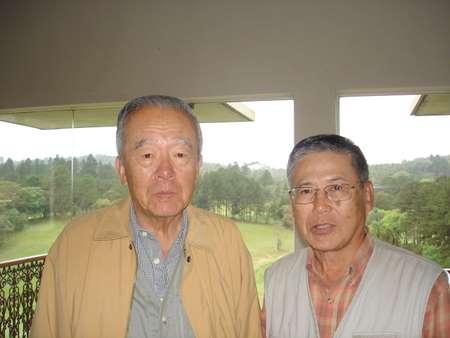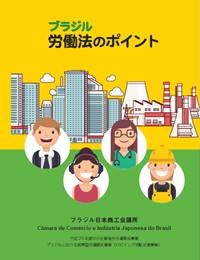ウジミナスのマルコ・アントニオ・カステロ・ブランコ社長が「鉄鋼業界の現状、ウジミナスのプロジェクトと挑戦」と題して、過去数年間の世界の経済成長率(GDP)は安定して4.8%前後で推移しているが、今年は石油・鉱物や農産物のコモデティ価格の高騰でインフレが上昇して世界平均のGDPは3.7%前後に減少するが、鉄鋼業界は中国の需要に牽引されて今後数年は増加の一途を辿ると見込まれている。
また発展途上国の鉄鋼生産も上昇の一途を辿っているが、鉄鋼業界の再編が進んでおり、大手鉄鋼メーカーのシェアが拡大しているが、今年は原材料の石炭、鉄鋼製、鉄くずなどのコモデティ価格が急騰してコスト高を招いているが、国内経済が好調なブラジルの今年のGDP、インフレ率とも4.8%前後が見込まれている。
内需が好調で昨年の国内鉄鋼生産は3380万トン、外資のアルセロール・ミッタルが30%のシェアでトップ、ブラジル資本ではウジミナスが26%、ゲルダウ22%、CSN16%、しかし原材料の高騰で鉄鋼価格は上昇の一途を辿っており、製品価格に転嫁されてインフレ高騰の一因となっている。
ウジミナスの事業戦略として川上から川下までを網羅する経営多角化を進めており、川上事業としてミナス州セーラ・アズール地域での鉄鉱石や石灰鉱山開発での資源確保、コスト削減のための製鉄所のあるイパチンガやクバトンでの火力発電事業、ジョゼ・ボニファシオ製鉄所の増産、サンターナ・デ・パライーゾの鉄鋼所建設、リオ・ネグロ社やファザル社の鉄鋼商社での販売強化、クバトン港やインガ港及び鉄道などのロジスティック事業などに投資して、原材料調達から輸出港湾までの事業統合を進めている。
事業統合によるコスト削減でウジミナスの鉄鋼製品製造コストは世界平均の7.0%も低くて価格競争力があり、また国内鉄鋼企業でのトップの地位を固めて世界企業になるために鉄鋼増産、鉄鉱石確保、技術革新によるコスト削減と並行して環境保護推進も目指している。
500万トンのサンターナ・デ・パライーゾ製鉄所建設、鉄鉱石鉱山買収、ロジスティック整備に141億ドルの投資、ウジミナス・プロジェクトに対する新日鐵や三菱からの投資、付加価値の高いプレミアム圧延鋼板ヤ亜鉛メッキ鋼輸出、ハイテクノロジーの先進国向け圧板輸出に拍車をかけている。
また国際鉱物価格変動ヘッジ対策及び原材料確保のために、年産500万トンのJ・メンデス鉄鉱山を9億2500万ドル、鉄鉱石埋蔵量が18億トンと見込まれているパウ・デ・ヴィーニョ鉄鉱山をそれぞれ買収、ポートフォリオとして燐酸鉱鉱山やアルミナ鉱山の買収も進めている。
付加価値の高い鉄鉱石のペレット生産を進めるためにウジミナスでは大型投資を予定、港湾ロジスティックを進めるために、セペチバ湾内にターミナル建設の土地を買収して鉄鉱石輸出のコスト削減を図るが、これらの統合投資には莫大な資金調達が必要であり、自己資金以外に社会経済開発銀行(BNDES)、社債発行やユーロ債発行で資金調達を予定しているが、日伯経済交流では日本移民100周年を機会に両国経済交流の再活性化が進んできており、バイオ燃料の日本への輸出、ペトロブラスによる南西石油の買収、石油開発部門や自動車部門への日本企業の投資などが盛んになってきていると述べて講演を終え、田中信会頭から記念プレートが贈呈された。
正午からソフィテルホテルで開催された懇親昼食会には135人が参加、進行役は平田藤義事務局長が務めて、初めにウジミナス社のマルコ・アントニオ・カステロ・ブランコ社長、在リオ総領事館の福川正浩総領事、在サンパウロ総領事館の丸橋次郎首席領事、ジェトロの元サンパウロセンター所長で関西外国語大学の桜井悌司教授、日本ブラジル中央協会の常務理事で徳倉建設の桜井敏浩特別顧問をそれぞれ紹介した。
連絡事項では福川総領事は日伯双方が有する環境分野等での経験・科学的知見を集約し、気候変動対策、食料生産など関連する地球規模の課題への対応に、新たな日伯協力の具体的プロジェクトをアイデンティファイして、提言していく事を目指して環境フォーラムを10月13日から14日までリオ市のBNDES会議場、16日はべロオリゾンテ市FIEMG会議場で開催、リオではセルジオ・カブラル州知事カルロス・ミンク環境大臣、安井至東京大学名誉教授、ベロオリゾンテ市ではアエシオ・ネーベス州知事、リナルド・ソアーレス在ベロオリゾンテ日本国名誉総領事などが参加すると案内した。
3分間スピーチではソフィテル・ホテルのシンチア・カズコ・ハセ氏が60ルームを改修、朝食の無料サービス並びに和食も用意、ホテル利用者への車使用の無料サービスを案内、ブラジル日本移民100周年記念協会が主要団体であり、副コーディネーターを務める伊藤忠の田中一男社長は10月15日午後7時からにサーラ・サンパウロで開催される、六本木男性合唱団倶楽部のブラジル公演に会員200名を招待、作曲家の三枝成彰が会長、団員として元首相の羽田孜衆議院議員、ソムリエの田崎真也氏、日本赤十字社の近衛忠輝社長 奥田瑛ニ映画監督など早々たるメンバーが参加している。
続いて久光製薬の河田明社長は9月27日から10月5日にかけてイビラプエラ体育館で開催される第8回サロンパスカップ案内では、北京オリンピックでブラジル女子バレーボールが金メダルを獲得、ブラジル選抜の選手も多数参加するレベルの高いバレーボールが無料で見られると案内、フィナーレ花火大会in サンパウロの実行委員会事務局の荒木宏光氏は12月2日にインテルラーゴで日本の最高の文化である隅田川の江戸花火大会を再現するが、資金並びに輸送面での支援を要請した。
コンサルタント部会長などで活発に商工会議所活動を牽引したジェトロの元サンパウロセンター所長で現在は関西外国語大学の桜井悌司教授は2003年11月に日本企業にブラジルのイメージを浸透させるために浸透作戦を開始、2004年5月のFIESPミッションでは物造りサミットとして横田エンブラエル副社長、元ゴールデンベルグ科学技術相が参加してブラジルの技術をアピール、またブラジルの知られざる技術のビデオも作成、最近ではBRICs効果が現れてきており、JALがエンブラエルのジェット機を購入して日本市場に参入、ペトロブラスは南西石油を買収して市場参入の足がかりを築き、今年は移民100周年でブラジルがテレビや雑誌に取上げられており、ブラジルは技術の国であるという浸透作戦が上手く言っていると述べた。
日本ブラジル中央協会の常務理事で徳倉建設の桜井敏浩特別顧問は5月の日・アフリカサミットをきっかけに、8月30日から9月9日まで東・西・南部アフリカ向けにそれぞれ40名から60名のミッションを派遣、南部班に参加した桜井顧問はボツワナ、モザンビーク、マダガスカル、南アフリカを訪問、ボツアナは世界のダイアの1/3を生産して輸出ではトップ、2008年7月28日、ボツワナ共和国南部の都市Lobatse市(ロバッツェ)において、JOGMECボツワナ共和国・地質リモートセンシングセンター開所したが、引っ張りだこになっており、モザンビークでは日本と南部アフリカ諸国の官民協力による世界最大級のモザール・アルミ精錬プロジェクトやインフラ整備プロジェクトを急いでおり、マダガスカルではニッケル開発が行なわれており、南部アフリカのインフラは比較的良いが治安が悪くて2010年のワールドカップ開催が心配されるが、今回のミッションでは中国が輸出並びに資源確保のための投資が目立っていたが、プロジェクトの建設終了後も中国人が帰国しないで現地で定住化していると述べた。
対会議所代表交代挨拶ではMatsubara hotelのウイリアム・スドー氏が紹介され、新入会員紹介ではロリン・弁護士事務所のアントニオ・カルロス・ロリン弁護士が田中信会頭から会員証が授与された。

講演するウジミナスのマルコ・アントニオ・カステロ・ブランコ社長

熱心に講演を聞く参加者

左からウジミナスのカステロ・ブランコ社長/田中信会頭/丸橋次郎首席領事

ウジミナス社カステロ・ブランコ社長と進行役の平田藤義事務局長
![a-08-09-18-ctge-aa-470.jpg[1].jpg - 109.94 Kb](/images/old_news/811-a-08-09-18-ctge-aa-470.jpg1.jpg)
![a-08-09-18-ctge-geral-ab-600.jpg[1].jpg - 152.16 Kb](/images/old_news/811-a-08-09-18-ctge-geral-ab-600.jpg1.jpg)





![a-08-09-11-cj-ab-600.jpg[1].jpg - 124.81 Kb](/images/old_news/808-a-08-09-11-cj-ab-600.jpg1.jpg)
![a-08-09-11-cj-ba-600.jpg[1].jpg - 150.26 Kb](/images/old_news/808-a-08-09-11-cj-ba-600.jpg1.jpg)
![a-08-09-11-cj-aa-600.jpg[1].jpg - 149.94 Kb](/images/old_news/808-a-08-09-11-cj-aa-600.jpg1.jpg)